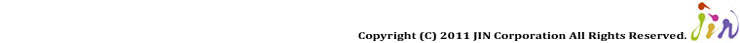国際協力プロジェクト
JICA ナイジェリア国 連邦首都区における栄養改善能力向上プロジェクト
| 分野 | 栄養改善 |
|---|---|
| 事業形態 | 技術協力 |
| 期間 | 2019年2月から2024年11月まで |
事業の背景
|
|
|
2歳未満の乳幼児の母親を対象としたフォーカスグループディスカッションの様子 |
ナイジェリアでは、5歳未満児の慢性的な栄養不良を示す成長阻害の割合が32.9%(132ヶ国中98位)、急性の栄養不良を示す消耗症の割合が7.9%(130ヶ国中93位)(2016年「世界栄養報告」)と高く、深刻な栄養課題を抱えています。
栄養状況の改善にあたって、ナイジェリアでは国家食料栄養政策に基づき、国レベルおよび地方レベルで省庁横断的な食料・栄養委員会が設置されていますが、それが集落レベルにおける包括的かつ実践的な活動に繋がっていません。ナイジェリア政府はこうした状況に加えて、連邦首都区において集落レベルのスタッフの能力を強化すべく、日本政府に技術協カプロジェクトを要請しました。
基本方針
『3分野からの介入を軸に、食を通じた栄養改善に取り組む』
|
|
|
ターゲットグループメンバーが栄養研修で3色食品群毎に食材カードを分けている様子 |
栄養課題の背景には、栄養に関する知識の不足、衛生観念の欠如、栽培する農作物の選択、農産物の生産量と栽培技術、家計管理や食料備蓄管理の計画性の不足など複合的な要因があります。そこで当プロジェクトでは、「栄養・保健衛生」、「農業」、「生活改善」の3分野に基づいた介入アプローチを開発し、主に妊産婦、2歳未満の乳幼児とその母親がいる世帯の食事の質と量、多様性の向上に取り組みました。また、パイロットサイト全体の住民にも栄養課題の改善を目指した活動を行いました。
『マルチセクター体制の整備』
上記の複合的な要因に対応するためには、関係者間の連携が鍵となります。しかし、上記3分野はそれぞれに異なる省庁の管轄であるため、協働していくのが難しい状況でした。そこで、当プロジェクトがマルチセクターによる活動実施体制を整備し、異なる省庁関係者による連携の仕組みの確立に取り組みました。
主な活動
第1期(2019年2月~2021年1月)は、プロジェクトの活動対象の村を3村選定し、それぞれ農家の夫婦20組に対して「栄養・保健衛生」、「農業」、「生活改善」の3分野の研修を実施しました。
第2期(2021年3月~2022年2月)は、対象である3村の対象グループに加え、サブグループを新たに設置し、3分野の研修を行い、より多くの住民の知識や技術の定着を図りました。さらに、それら3村では栄養・農業・保健の啓発イベント、小学校の教員向けの栄養・保健研修、保健センターの職員向けの栄養・保健研修など、栄養改善に係る知識や技術が3村の住民全体に広まり、行動や実践に繋がることを目的に普及活動を行いました。
「栄養・保健衛生」の研修では、食品群、妊婦・授乳婦に必要な栄養、乳児に必要な栄養、下痢の原因と予防等のテーマを扱い、食事の改善や、手洗いなどの衛生行動の改善に繋がる知識や技術を伝えました。
「農業」の研修では、栽培計画の立て方、肥料散布、病害虫対策、市場調査等のテーマを扱い、住民が農業収入の増加を通じて栄養価の高いものを購入できる、あるいは住民が豆や葉菜類など栄養価の高い農作物を自分で栽培し、消費できるようにするための技術や知識を伝えました。また、サイト毎にデモ圃場で栽培実習(メイズ、ビタミンA強化キャッサバ、大豆、ササゲ、アマランサス、ジュート、カボチャ、ニンジン)も行い、各住民が自分の畑でもいくつかの作目を栽培しました。
「生活改善」の研修では、食品加工、収穫後処理・保管、家計・備蓄管理、ジェンダー等のテーマを扱い、栽培した収穫物やそこから得た収入を家庭内で適切に活用するための演習を行いました。これらの研修を通じ、3村の住民の中から、活動で得た知識や技術を実践する多くの好事例が確認されました。
第3期(2022年2月~2024年11月)では、新たに6村を選び、第1期・第2期でまとめた教材を基に、より多くの住民に研修を行いました。また、それらの6村で、妊婦、2歳未満の子どもとその母親、世帯主を対象に、地域の栄養状態や、農業や暮らしの実態を調査しました。調査の結果、プロジェクトが介入したことで、人々の食事の質や栄養、農業、生活面で様々な良いインパクトがあったことが確認されました。
そして、最後に、プロジェクト終了後も「食を通じた栄養改善」のための活動を続けてもらえるよう、運用ガイドラインやマニュアルを作成しました。これらは、特別会合の場において関係職員によって承認され、今後も持続的に活用されることの重要性が確認されました。
|
|
|
|
|
栄養改善に関する啓発イベント |
研修で学んだ技術に基づいてササゲを栽培する農家 |
小学校での簡易手洗い装置の実演 |
~JICAのWebサイトでの紹介~
→『栄養改善パートナー通信』第2巻第2号 世界で働くパートナー vol.30 ~専門家編~「ナイジェリア国連邦首都区における栄養改善能力向上プロジェクト」(2023年12月22日)はこちら(外部リンク)
→『mundi』2020年1月号(プロジェクトの紹介)はこちら(外部リンク)
→『ODA見える化サイト』はこちら(外部リンク)
コンサルタントの想い
|
|
|
事業部 次長 園山英毅 |
プロジェクトの目的はナイジェリアの子どもや女性たちの栄養状態を「食の改善」を通じて改善することでしたが、その手段として現地の人々に単に栄養や食事について学ぶ機会を提供するだけは十分な効果を期待することが難しい状況でした。
栄養問題の背景には「栄養のある食事をとりたくても食材となる作物を畑で十分に栽培できない」「収入や家計管理が十分でなくマーケットで食材を買うことができない」「妊娠・授乳中の女性や乳幼児期の子どもの食事への配慮に関する夫や家族の理解が足りない」といった、より複雑で多面的な問題が隠れていて、だからこそ、それに包括的に対応する「マルチセクター」の支援が必要とされていたわけです。
5年8カ月にわたった活動の運営は、コロナ禍や治安悪化などの困難にも見舞われ、決して簡単なものにはなりませんでした。しかし、マルチセクターチームのメンバーとして現地の農業局や保健局から集められた職員や普及員の人たちが助け合いながら現場での活動に熱心に取り組んだことで、現地の多くの人々の知識や意識、行動に様々な改善が見られ、「こんなに食事や生活が変わった」という沢山の喜びの声を受け取った際はとても感慨深いものがありました。今後もこの支援の成果を活かして、より多くの人々の笑顔につながる活動が現地で続けられていくことを切に願っています。