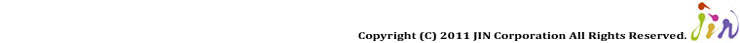国際協力プロジェクト
ウガンダ国綿花生産等を通じた難民・ホストコミュニティの生計向上に係る情報収集・確認調査(QCBS)
| 分野 | 農業開発 |
|---|---|
| 事業形態 | 情報収集・確認調査 |
| 期間 | 2023年6月から2024年6月まで |
事業の背景
|
|
|
パイロット活動を行った綿花圃場の様子 |
ウガンダ政府は、伝統的に難民に寛容な政策を取っており、主に南スーダン、コンゴ民主共和国等の周辺国から150万人を超える難民を受入れています。特に受け入れの多いウガンダ北部は、約20年続いた内戦の影響を最も強く受けた地域でもあり、開発の遅れにより、貧困・脆弱な層が多い傾向にあります。このため、難民の方々だけではなく、元々その地域で暮らしているホストコミュニティ(HC)の住民を含めた零細農業従事者の生計を向上させることが重要となっています。
ウガンダ北部において難民とHCの住民双方が生産者として携わっており、今後も成長が見込まれているのが、綿花産業です。当産業は、綿花の生産・加工の過程において、更なる難民雇用の促進と生計向上に資する産業となり得る可能性を秘めており、難民やHCの小規模農家を取り込む形で発展するために必要な取り組みや留意点を整理することは非常に重要です。
本事業では、ウガンダ北部の綿花産業が、難民とHC双方の生計向上に資する可能性について調査を行い、綿花産業としての競争力向上に必要な施策や、今後JICAが類似事業を行う際のアプローチ等の検討を行いました。
基本方針
|
|
|
収穫された大量の綿 |
はじめに、本事業では、①難民とHCの現状と、②ウガンダ産綿花の栽培・普及の現状と課題について調査を行いました。①に関しては、食料や土地へのアクセスが限られる難民居住区での厳しい生活の実態や、難民を受け入れる側の生活の実態について、難民・HCにインタビューを行いました。また、難民・HCを取り巻く様々なステークホルダーによる難民・HC支援についてもその実態を把握しました。②に関しては、ウガンダの農産品における綿花の位置づけや、生産動向等を把握し、綿花農家による生産~綿花の普及に至るまでの一連の流れや仕組みについて情報収集を行いました。
本事業では、上記の各種調査に留まらず、難民居住区内において、難民・HCを対象とした綿花栽培のパイロット活動を実施したことも大きな特徴です(実施期間:2023年7月~2024年2月)。実際に、難民・HCが共に綿花栽培を行うことで、綿花栽培が彼らの効率的な収入活動に繋がるのかという点や、協働することで生まれる課題や教訓は何なのかを整理し、本事業の成果として取りまとめました。
主な活動
調査では、ウガンダ北部のアチョリ地域・西ナイル地域の綿花栽培農家に聞き取りを行い、綿花栽培及び営農体系の実態の把握に努めました。その結果、綿花栽培の営農上の利点として、食料として消費されないので収穫したものを全て現金化できることや、農家の住居近くに集荷場所が設置されるため、売るのが楽であること(かつ売上が即金で手に入る)等が明らかになりました。一方、不利点としては、害虫が多いことや、食料作物ではないため販売できなかったときに使い道がない(食べられない)等が分かりました。
また、綿花栽培農家へのインタビューだけではなく、紡績・製織・縫製会社、流通・輸出業者等にも聞き取りを行うことで、綿花産業を取り巻くサプライチェーンの構造を明らかにしました。また、ウガンダ綿花産業の課題をステークホルダー毎(生産者・集積場から輸送・輸出事業者・ウガンダ政府機関)に抽出・分析を行うことで、ウガンダ国内での綿花の付加価値を高めるための施策についても提案を行いました。
パイロット活動については、難民・HCの農家各20名(計40名)が参加し、現地NGOが再委託先として実施支援・管理を行いました。生産作物は、難民の厳しい食料事情を鑑み、換金作物である綿花だけではなく、食料作物であるトウモロコシを対象として追加しました。
また、本活動を行う上で「ブロックファーミング」という手法を導入し、その実施可能性や運営上の課題、改善策を抽出しました。この手法は、政策的に大型農地の開墾を促進することが特徴です。土地を持たない難民の方々は、HCの住民から個々に農地を借りていたため、耕作面積が小さかったり、利用条件に制限があったりしましたが、このスキームにより大規模で効率よく作物を栽培することができるので、広い土地が必要になる綿花栽培には適していると考えました。また、難民とHCの農地を隔てず共同作業を行うことで、両者間のより良い人間関係が構築できることが分かりました。
本事業の結果、厳しい生活を強いられている難民の方々に対しては、ブロックファーミング等の手法により、HCと協働しながら食料作物と換金作物(今回は綿花栽培)を行うモデルが生計向上のために重要であることが示されました。
|
|
|
|
|
難民居住区の居住エリアの様子 |
パイロット活動に参加した難民とHC |
生育した綿花の様子 |
コンサルタントの想い
|
|
|
代表取締役 大野康雄 |
この事業に従事し、難民の方々の現状を詳細に調査しましたが、皆さん本当に苦しい生活をされているのが確認され、心を痛めました。世界食糧計画からの難民への食料配給の量が激減しており、ほとんどの難民の方々が、生きていくために最低限必要とされる食料の30%分しか配給されていない状況となっています。この背景には、世界的な内戦(ウクライナ・パレスチナ・スーダンなど)の勃発が大きく影響しており、国際機関も予算不足から必要な手当てをできなくなってきているのです。このような状況の中、少しでも難民の方々やウガンダのHCの皆さんに何かできないか、調査中ずっと考えていました。調査後も具体的なアクションを早急に起こせないか、JICA関係者とも相談してきました。今後も難民・HCの皆さんのためになることを真摯に考えて、実現に向けて努力していきたいと思います。